No.010
Issued: 2003.10.02
第10講 秋深し、瀬戸内法はなんのため?
プロローグ
Aさんセンセイ、今日は突き抜けるようなさわやかな秋の青空ですね。こんな日になにも研究室で講義することないじゃないですか。「書を捨てて街に出よう」ですよ。

H教授昔、マルクスが愛してやまなかったゲーテの至言がある。正確には覚えてないけど「緑なす現実の豊かさ! それにくらべ学問のなんと灰色なことか!」だったかな。
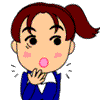
Aさんゲーテさんもいいこというじゃないですか。じゃ、本日の講義はなしですね。
H教授(厳かに)でもねえ、ぼくらはこの現実をより豊かに緑なすために、時に灰色の肥料を播かねばならないんだ。キミには今がまさにそのときなんだよ。
Aさん(虚を突かれて)うーん、なるほどねえ・・・でも、ちょっとカッコ良すぎるなあ。だれの受け売りなんですか?
H教授へへ、商売のネタをばらすわけにはいかないよ。さ、始めるぞ。前講以降のトピックスでなにがあった?
ディーゼル排ガス規制強化 -トピック・1
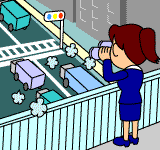
Aさんえーと、関東の自治体では10月からディーゼル車の排ガス規制を独自にはじめています【1】。
環境省もディーゼル排ガスの規制強化をしてますけど、環境省は地方自治体の動きに少なくとも表面上は苦い顔してるようですね。一体どうしたんでしょう?
H教授さあ?
Aさんえ? 知らないんですか? そういえば、この時評ではいちども自動車排ガス問題を正面から取り上げてないですね。センセイはそれほど環境問題としては重きを置いてないんですか。
H教授いや、そんなことないよ。重要な問題に決ってるじゃないか!
Aさんえ? じゃ、どうして? どうして?
H教授簡単さ、よく中身を知らないからだ。なんせ、ぼくは役人時代いちども自動車排ガス問題にタッチしたことがない。知ったかぶりして、変なことをいえば、どっと批難の投書が来るもんなあ。
Aさん(呆れて)しょうがないセンセイですねえ。じゃあ、細かいことはいいけど、なぜ今、ディーゼル排ガスが問題になってるんですか。
H教授ひとつは都市のNOx【2】問題が改善していないんだけど、ディーゼル車は相対的にガソリン車より、N0xの負荷が高いということ。もうひとつはやはり都市を中心に環境基準の達成が芳しくないSPM(浮遊粒子状物質)【3】対策だろうなあ。
Aさんじゃ、ガソリン車よりディーゼル車の方が環境にやさしくないんですか?
H教授そりゃ一概にいえない。環境問題のなにをターゲットにするかで変わってくる。
ディーゼル車の方が燃費がいいよね、と言うことは、走行距離当たりのCO2負荷はディーゼル車の方が低いということになる。つまり温暖化対策という観点からはディーゼル車の方がいいということだよね。
一方、NOxやSPMとなると話は逆になる。とりわけ欧米ではPM2.5【4】が発ガンに寄与しているといってうるさいんだけど、ディーゼル排ガスにはPM2.5が多いらしい。
AさんPM2.5?
H教授環境基準【5】が決められているSPMは10ミクロン以下の微粒子と定義されているんだけど、2.5ミクロン前後の超微粒子に発がん物質が多く含まれているらしいんだ。だから、それを特にPM2.5と呼んで区別している。
で、ディーゼル排ガスにはそれが多いらしいってことだ。
Aさんなるほどねえ、一長一短というわけですか。
H教授問題はガソリン車かディーゼル車かということより、より環境負荷の小さい公共交通機関の充実だと思うよ。だから第9講でもいったけど、自動車諸税は道路整備だけじゃなくて、環境負荷対策と公共交通機関の助成にも充てることを考えるべきだ。
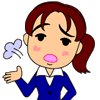
Aさん自分がクルマ乗り回してて、よくそんなこと言えますね。

H教授ぼくが東京にいるときはクルマなんか持ってなかったよ。公共交通機関が充実してたからな。
Aさん駐車場代が高いのと、大都会のど真ん中で運転するのが怖かっただけでしょう(笑)。
でもクルマに関してはグリーン税制【6】が敷かれたじゃないですか。これで少しはよくなるんじゃないですか。
H教授大気汚染ということでいえばそうかもしれない。でも、全面的には賛成しがたいなあ。
Aさんえ、どうして? センセイの普段の言動からいえば、大賛成と思ったけどなあ。
H教授年々クルマの排ガスや燃費は改善している。だからといって、毎年、毎年、より「環境にやさしい」クルマに買い換えるのが「環境にやさしい」ライフスタイルだとは思えないなあ。
クルマとか家とかは一生大事に使うという精神も必要じゃないかなあ。廃棄物問題だってあるしなあ。
Aさんそうか、センセイのクルマはほんとひどいポンコツですもんねえ。ま、一所懸命高い税金を払ってください。
H教授よけいなお世話だ。
VOC規制宣言 ―トピック・2

H教授ところでいまSPMの話をしただろう? SPMが改善しないのはVOC(揮発性有機化合物)【7】のせいだと言って、環境省は固定発生源からのVOCの法規制を本格的に目指すことにしたらしい。
ぜひボクのときのリベンジを果たしてほしいねえ。
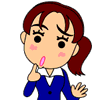
Aさん?? どういうことですか。
H教授第8講でノンメタンハイドロカーボン(NMHC)【8】の話をしただろう? 法規制を目指したけど挫折したって話。
実は、NMHCってのはVOCの大半を占めているんだ。NMHCはオキシダント【9】の原因物質なんだけど、同時にSPMの主犯とまではいかないまでも重要な共犯らしい。大気中に放出された揮発性炭化水素系物質が細かい水滴みたいになってSPMの相当部分を占めているんだ。
Aさんじゃ、NMHCで統一すればいいじゃないですか。
H教授NMHCは炭素と水素だけの化合物だけど、VOCはもう少し定義が広くて、炭化水素に酸素や窒素が入ったものを含んでいる。ホルムアルデヒドなんかのようにね。
Aさんあーあ、頭が痛くなってきましたよ。
H教授わかった、わかった。まあ、ともかく、環境省がVOCの排出抑制に向けた法規制の検討を始めたということと、その目的がSPMやオキシダント対策にあるということだけは押さえておいて、今後の経緯に注意を払っていこう。年内にも検討会報告が出て、次期国会に法案を提出する見込みのようだよ。
知床、世界自然遺産に ─トピック3
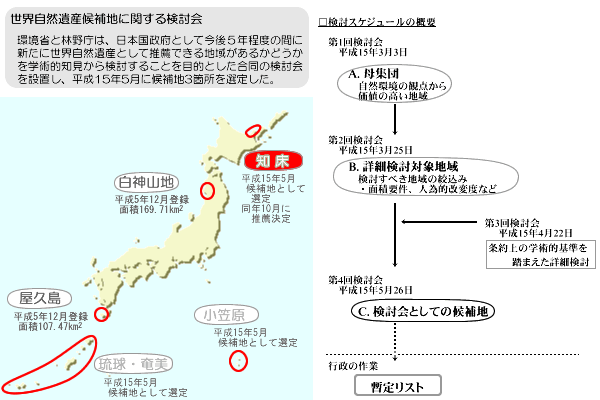
図:日本の世界自然遺産(登録地2箇所+候補地3箇所)および、世界自然遺産検討会(環境省・林野庁合同)について
(環境省資料等より作成)
H教授じゃ、最後のトピック。ユネスコの世界自然遺産って知ってるよね。日本では白神山地と屋久島が登録されている。
環境省と林野庁は、知床を日本で3番目の自然遺産として登録するよう推薦することを決めた【10】。
Aさん確か知床、小笠原、琉球・奄美の3箇所に候補地を絞ったんですよねえ。なぜ知床だけになったんですか?
H教授自然的価値からすれば、どれも資格あると思うよ。でも自然遺産というのは、きちんとした管理のもとで守られることが国内法で担保されてなければダメなんだ。小笠原や琉球・奄美は自然遺産となれば観光地としても箔がつくことは間違いないから地元では熱望しているのも事実だけど、同時に小笠原だったら空港問題、琉球・奄美だったら赤土流出【11】とか干潟埋立みたいな開発問題があって、管理上の条件を満たしていないということじゃないかなあ。
Aさんなるほど、なかなか一筋縄ではいかないんですね。
さ、トピックスはこの程度にして、今日のメインテーマはなんですか?
瀬戸内法30年、浄化槽法20年

H教授今年は瀬戸内法30年、浄化槽法20年なんだ。その話をしようか。
Aさん瀬戸内法は何回か聞いたけど、浄化槽法なんて知らなかったなあ。ワタシが生まれた年にできたのか。
H教授(鼻で笑って)また年齢詐称だ。そのセリフ聞き飽きたよ。
Aさんヒッドーイ!
H教授(無視して)長くなるから、今講はどっちかひとつにしよう。どっちがいい?
Aさん(不承不承)瀬戸内法の話は断片的にしか聞いてないから、今回はきちんとそれを話してください。
瀬戸内法の世界 ・・・その1 瀬戸内法とはなにか
H教授わかった。じゃ、浄化槽と下水道の話はこの次にしよう。ところで瀬戸内法ってどんな法律だ?
Aさん確か正式名称は「瀬戸内海環境保全特別措置法」ですよね。瀬戸内海の環境保全のために特別の措置をとることを定めた法律です。
H教授どんな特別の措置?

Aさんそんなことがすんなり答えられるようならセンセイのゼミなんて来てませんよ!
H教授(たじたじとして)そっか。まあ、そうだろうなあ。仕方がない、ぼくのゼミに来るのはキミ程度の学生しかいなかったんだもんな。
Aさん類は友を呼ぶだったっけ、同病相憐れむだったっけ、ムカシの人はいいことを言いますねえ。

H教授(呆れ果てて)もういい黙っててくれ。じゃ、特別講義をはじめるぞ。
瀬戸内法はもともとは「瀬戸内海環境保全臨時措置法」といったんだ。そしてそれを執行するために、当時の環境庁に瀬戸内海環境保全室、通称「瀬戸内室」ができたんだ。
ボクはそこにいたんだけど、その瀬戸内室も瀬戸内海環境保全基本計画の改定を置き土産に一昨年、環境省誕生とともに閉鎖性海域対策室と名前を変えちゃった。
Aさんなんでそんな法律ができたんですか。地域を特定した環境保全のための法律なんて他に例がなかったわけでしょう?
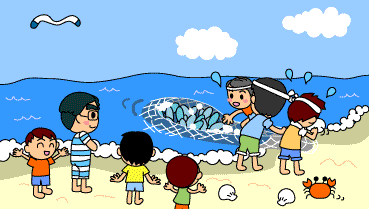
昭和30年代の瀬戸内海の浜(イメージ画)
H教授それだけ瀬戸内海の環境破壊がひどかったということだし、瀬戸内海が沿岸住民にとっていかに大事なものだったかということだろうなあ。
昭和30年前後は大阪湾にだって至るところに浜や干潟が広がってた。堺の浜寺まで泳ぎに行ったり、地引網のなかで魚を手づかみで採りに行ったのを今でも思い出すよ。
Aさん浜寺って、コンビナートのど真ん中じゃないですか!
H教授そうそれくらい当時の大阪湾はきれいだったし、魚の宝庫だったんだ。だが高度成長が始まり、昭和40年代に入った頃、白砂青松を謳われた瀬戸内海は瀕死の状態になっていた。
大阪湾の自然海浜はほぼ埋め立てられ、瀬戸内海全域の各所にコンビナートが出現し、汚水を垂れ流し、赤潮が頻発していたんだ。
Aさんほんとですか、講釈師見てきたようなウソをつき、じゃないんですか。
瀬戸内法制定前夜
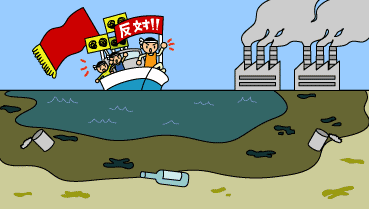
昭和40年代の瀬戸内海の浜(イメージ画)
H教授いい加減にしろ。ぼくは昭和43年から2年間、岡山の鷲羽山で瀬戸内海国立公園のレンジャーをしてたんだ。第7講で言っただろう!【12】
後ろに水島、前に番の洲のコンビナート。浜には黒いオイルが打ち上げられ、漁民が水上デモをしていたのを思い出すよ。
Aさんじゃ、センセイは当事者だったんじゃないですか。瀬戸内海国立公園のレンジャーだったんだから、それを食い止めるのが仕事じゃなかったんですか!
H教授残念ながらそうじゃなかったんだ。
瀬戸内海国立公園と言っても、実質的に開発規制などの権限があるのは、景勝地や展望台のある岬だとか小っちゃな島だけ。
当時、すでに瀬戸大橋の建設は閣議決定されていたけど、厚生省の国立公園部、つまり今の環境省自然環境局なんて一言も口が挟めなかったんだから。
Aさんセンセイ、そりゃ情けなさ過ぎます!
H教授でも、その頃から風向きが変わり始めた。公害反対とか自然破壊反対の声が燎原の火のように全国に広がった。で、一気に公害規制が強化され、環境庁も誕生した疾風怒濤の時代だった。その最先頭を走ったのは瀬戸内海なんだ。
漁民や市民の声に押されて自治体が動き出し、昭和46年に瀬戸内海環境保全知事・市長会議が誕生、瀬戸内海環境保全憲章を制定。翌年には瀬戸内海の環境保全のための特別の法律の制定を要求したけど、政府はまったく逃げ腰だったことから、議員立法で瀬戸内海だけを対象とした環境保全の法律を作ろうとしたんだ。これが「瀬戸内海環境保全臨時措置法」で、昭和48年、全会一致で上程可決された。
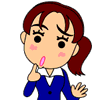
Aさんでも、議員立法ってそんな珍しくないんでしょう。
H教授ところがギッチョンチョン、ほとんどの議員立法と称するやつは立法作業などをする黒子の省庁がいるんだ。瀬戸内法だけはその黒子役をぎりぎりまで沿岸府県の環境部局が務めたそうだよ。
瀬戸内法行政の先駆性・先見性と限界
Aさんま、でも問題は法律の中身でしょう。当時、いっぱい環境関係の法律が出来たじゃないですか、なにが特徴だったんですか。
H教授ぼくの独断と偏見で言えば、先駆性、先見性だよね。今日の環境行政を20年か30年前に先取りしたんだ。
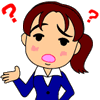
Aさんそんな抽象的に言われたってわかりませんよ。もっと具体的に。
H教授まず、昔っから行政ってのは中央集権でなおかつタテ割りだって知ってるよね、今日でもそうだし、環境省だって中ではタテ割りだ、水、大気、自然、ごみ などとね。
そんななかで、異色の法律だったと思うよ。タテ割りと中央集権を排除するという理念があった。
Aさんえ、どういう風に?

H教授この法律の目的規定のなかに瀬戸内海の環境総体、つまり水もごみも自然も魚類資源も守るってなっているんだ。しかも瀬戸内海に流入する河川の源流域までも一体として法律の対象地域とした。そしてそのために他省庁の施策も取り込んで、瀬戸内海環境保全基本計画っていうビジョンを作ることを定めた。いまの環境基本計画だとか、この3月閣議決定された循環型社会形成推進基本計画の源流の少なくとも一部はここだと思うよ。ま、実際に計画ができたのは臨時措置法制定から5年も経ってからだったけどね。
そして、お目付け役の審議会ってのがある。一般的に審議会の委員はほとんどの場合、各省庁の推薦で決まるんだけど、瀬戸内の審議会の場合は半分くらいが関係府県の知事または知事の推薦する人だったんだ。
そういう意味では、瀬戸内法を軸とした行政、つまり「瀬戸内法行政」は、地方分権とか地方主権のハシリと言っていいんじゃないかな。だから思い切った個別施策もいくつかできた。
Aさんへえ、どんな?
H教授排水の規制は水質汚濁防止法、いわゆる水濁法で決まっていて、随分厳しくしたんだけど、結局は濃度規制だった。そんななか、CODの量規制をやった。一気に半分にするってしたし、しかも、それを実現した。いまの東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の総量規制【13】の原動力になった。
もうひとつは埋立。最初は原則禁止を謳おうとしたが、一部地域の異論もあり、瀬戸内海の特殊性に配慮しなければならず、その運用に関しては審議会にゲタを預けたんだけど、産業界からも霞ヶ関からも原則禁止に特に強い異論はなかったらしい。
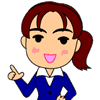
Aさんで、審議会から答申されたのが、前々から話に出ていた「埋立の基本方針」【14】ですね。
H教授そういうこと。つまり、瀬戸内法っていうのは、自治体・市民・マスコミ連合が国会を動かし、政府や産業界を押し切って作ったもので、しかも、その執行組織である瀬戸内室を環境庁のなかに作らせたんだ。
それ以降も、こうした出自の特異性から瀬戸内法行政は瀬戸内室と知事・市長会議と関係府県の自治体の環境部局に漁協や衛生団体も加わって作られた瀬戸内海環境保全協会の三位一体で進めるという特殊な行政になった。最近でこそ、パートナーシップ云々って言いだすようになったけどねえ。
Aさんそれはともかくとして、その基本計画とか埋立への特別の配慮ってのはどうなったんですか。
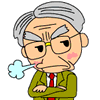
H教授うーん、志は高かったが、ハードルも高かった。臨時措置法は名前の通り、3年間の時限立法だったんだけど、その間にオイルショックがあり、風向きが変わった。つまり環境風がぴたっと止まった。で、さらに2年延長して、ようやく基本計画について各省庁の合意を取り付けられたのは、政府提案の後継法、つまりいまの瀬戸内法になる直前だった。ま、それでも閣議決定だから、各省も尊重する義務があるはずなんだけど、長い間軽視されてた。
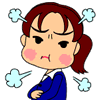
Aさんなんでえ。閣議決定ってそんな軽いものなんですか。
H教授いや、計画そのものが極めて抽象的、定性的なものにならざるをえなかったんだ。多分、環境風が吹かなくなり、他省庁との調整が難航したからだと思うよ。
でも、「埋立の基本方針」については辛うじて「厳に埋立は抑制すべしであり、やむをえず認める場合は・・・」って形で答申がでて、ぎりぎり理念的に埋立抑制を謳い込めた。以降の瀬戸内室の重要業務はこの埋め立て案件の処理だった。
Aさん理念だけじゃしょうがないじゃないですか。だってそれからあとも山ほど埋立ててるじゃないですか。
H教授ひとつは「駆け込み」だよね。法施行前に免許取得してしまっていた。もうひとつはこの「基本方針」が抽象的・理念的で抜け穴だらけということもある。
Aさんじゃ、まったく意味はなかったんですか
H教授そんなことはないよ、法施行前と後を比較したら随分埋め立ては減ったよ。それにね、表に出てくるまえに、埋立の基本方針の「厳に抑制すべし」を根拠に埋立計画をあきらめさせたり、縮小させたり、あるいは人工の藻場や干潟を作らせたりした。いまでいうミティゲーション【15】だよね。それは他の海域より先進的だったと思うよ。だって、埋立そのものに関しては環境庁はニュートラルなんだけど、唯一瀬戸内海だけは「厳に抑制すべき」という理念を謳ってるんだから。
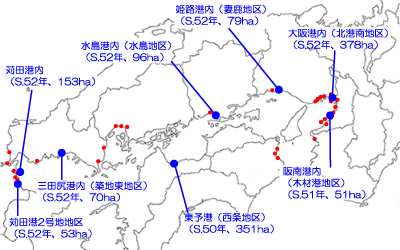
昭和50年〜52年免許の埋立事業
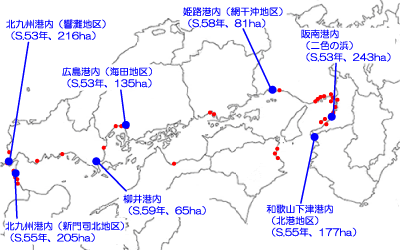
昭和53年〜59年免許の埋立事業
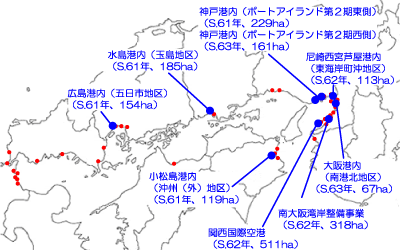
昭和60年〜63年免許の埋立事業
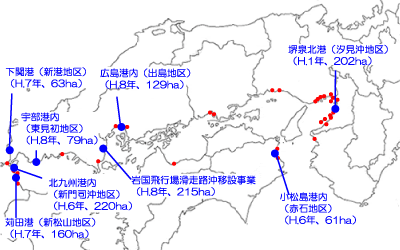
平成元年〜8年免許の埋立事業
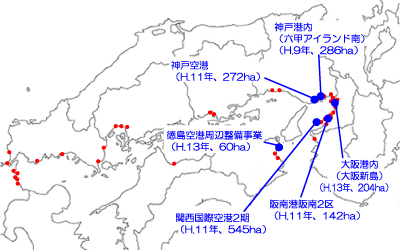
平成9年〜13年免許の埋立事業
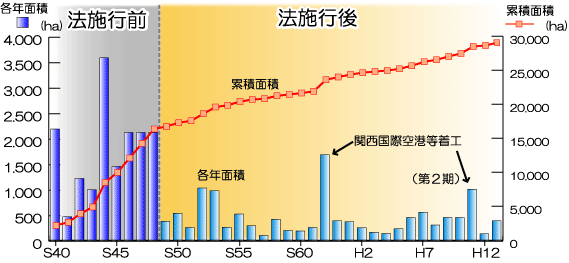
Aさんセンセイも計画をとめさせたり縮小・変更させたことがあるんですか?
H教授そりゃあるよ。でも守秘義務があるからいえない。
Aさんウソばっかり、言いたくってうずうずしてるくせに。
埋立て秘話
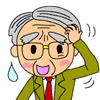
H教授わかった、わかった。でも固有名詞はださないよ。公有水面埋立の手続きを進めるまえの事前調整の段階で※、ある県がリゾート法【16】がらみの計画で島の海岸を埋め立てて別荘分譲したいと言ってきて、ぼくのところに話が上がってきた。
国民共有の財産である海を埋め立てて個人に切り売りするようなものは到底「やむをえず認める場合」とは言い難いって、つっぱねちゃった。
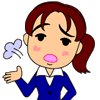
Aさんセンセイは別荘なんて到底持てそうにないからひがんだんでしょう。いやらしいなあ。
H教授うるさい! 県は怒ってトップまで直談判に来たけど、首を縦に振らず、とうとう「別荘分譲のための埋立は<やむをえず認める場合>に該当しない」という通達を出しちゃった。県には恨まれたけど、結果的にはリゾート法はひどいことになってるもんなあ。もしゴーサイン出してたら、いまごろ赤字抱えてうんうん言ってるよ。宮崎のシーガイアもぶっとんだしねえ。
大体第三セクターってのは、役所の公平性と民間の効率性のいいとこどりって触れ込みだけど、むしろ役所の非効率性、官僚主義と民間の営利主義の合体プラス無責任体制で、必ずしもうまくいってるとは言えないよな。
Aさんま、その話は聞き飽きたからいいです。他には?
H教授なんだ、これから大演説ぶとうと思ったのに。ま、いいや。
それからね、ある県が人工島で空港計画を持ち込んできた。ところがなにも人工島を作らなくたって、沿岸には製鉄会社の広い遊休地があるんだよねえ。
だから、「やむをえず認める場合」かどうか疑わしいってつっぱねた。採算性や必要性にもともと疑問はあったけど、環境庁はそこまで言うわけにいかないし、最後の落としどころはその遊休地を使い、不足分はそのまわりを埋め立てて空港を作るんだったらやむをえないかと思ってたんだ。ところが県はあっさりと方針変更して内陸部に計画変更した。
Aさんへえ、それでどうなったんですか。
H教授住民の反対運動でにっちもさっちも行かなくなり、最近になって財政難で計画中止に踏み切ったらしいよ。大体これだって採算がとれるわけがないんだ。
Aさんいつごろの話なんですか。
H教授両方ともバブル崩壊前夜のころだ。
臨時措置法から現行法に
Aさんへえ、センセイには浅見の迷(センケンノメイ)があったんですねえ。ま、その話はそれくらいにして、臨時措置法から現行の特別措置法になってなにが変わったんですか。

H教授うーん、環境風が止んだ後の特別措置法への移行は相当難航したようだよ。それでも、燐(リン)【17】の抑制指導だとか自然海浜保全地区制度【18】の導入だとか、いくつかの新しいものを持ち込めた。燐(リン)って知ってるよね。
Aさんええ、富栄養化、つまり赤潮なんかの原因物質でしょう。窒素もそうじゃなかったですか。
H教授そうそう、でも定性的にはそうは言えても、実証的・定量的に証明するのはむつかしい。そんななか、辛うじて燐だけは抑制指導を明示できた。
ボクが瀬戸内室に行ったのは、そのずっとあとで、なんとか窒素の抑制指導も持ち込めないかといろいろやったけど、ダメだったね。実証的・定量的に窒素抑制の必要を証明しろの一点張りでねえ。でも、それから十数年、いまじゃ燐も窒素も抑制指導どころか規制対象になっている。
Aさんへえ、それだけ科学が進歩したんだ。

H教授さあ、どうかなあ。むしろ環境に関しては、疑わしきは罰せよ精神が'90年代に入って、ようやく浸透してきたからじゃないかなあ。
そりゃ、他の役所は既得権益の保護のためにあの手この手で屁理屈をいい、政治家の手も借りて規制逃れをしようとするけど、むしろ、積極的に環境に打って出る方が予算や権限の拡大につながると見れば、方針変更は平気でするよ。'90年代から今日はまさにそういう時代なんだよ。
ただ、残念ながら瀬戸内法は、基本計画という今日でいう水環境総体の立派なビジョンを打ち出したんだけど、水質規制と埋立審査以外には、それを実現するための諸手段を自らは持っておらず、そのころ話題になった海砂採取にも豊島の廃棄物対策にも具体的には関与できなかった。
だから、環境庁は瀬戸内海環境保全基本計画の全面改定を打ち出したんだと思うよ。
Aさんへえ、やっぱり環境の時代が来たんだ。
H教授と、いう風にすぐ短絡してしまうところがキミのダメなところだ。
Aさんえー、どうしてですか?
F池随想
H教授いま選挙戦真っ只中だけど争点は専ら景気対策だ。公共事業の拡大を求める声だって今でもある。こうした声が相変わらずムダで採算の取れない公共事業を押し上げている。さすがに、物議をかもすような大型開発は消えたけどね。キミ、F池って知ってるかい?

Aさんええ、いつかゼミで連れていってもらいました。里山に囲まれたひなびた池だったですね。水鳥がいっぱいいて、まわりに閑静な遊歩道があって。
早く王子さまを見つけて、あの池のほとりでくちづけしてほしいなって思ったんですよ

H教授で、実行したのかい?
Aさん(きっとして)よけいなお世話です、セクハラじゃないですか! そんなことより早く先を言って下さいよ。
H教授わかった、わかった。数年前のことなんだけど、あそこのそばの山のてっぺんが大々的に切り崩されて駐車場と大きな建物ができちゃったし、池につづく斜面は伐開して芝生広場になっちゃったよ。
Aさんえー、じゃあ、あの池の雰囲気は台無しじゃないですか。民間が開発してるんですか?
H教授ちがうよ。キミの好きな県と市の公園づくりだよ。馬鹿でかい建物は「自然観察学習館」で、環境保全事業だそうだよ。何十億円もかけてるんだろう。
Aさんそんなあ...。
H教授その手のものがまだまだ至るところにあるよ。
ハコモノからソフトに変わらなきゃいけないんだけど、底辺では一向に変わっていないねえ。
瀬戸内計画改定

写真:(財)環境情報普及センター主催の 環境セミナーのポスター(H教授講演)
Aさんセンセイ、それより瀬戸内海環境保全基本計画の改定のポイントをまだ聞いてないんですけど。
H教授でも、もう紙数がない。やっぱり現役にまかせよう。
Aさんセンセイ、じつは読んでなかったりして...。
H教授(ぎくっ)バカ言うなよ。じゃ、いくつか指摘しておこう。
まずこの改定にあたって広く意見を募り、何回も公聴会をやったりした。いままでみたいに密室のなかで決めるという手法はとられなかった。
そして随所に見られる特徴は過去の開発のそれも含めて環境の復元・創造、つまりミティゲーションに力を入れていること。もうひとつは地域住民の意向の反映、参加を強調していることだと思うよ。旧計画では住民は啓蒙の対象、理解と協力を得る存在だったけど、もはや住民は保全の主体として位置づけられた。
Aさんでもコトバだけかもしれないでしょう
H教授もちろん、その危険性はある、というより高いと思うよ。この基本計画の実現を担保する諸手段を瀬戸内法は持っていないし、各省庁を横断的にフォローアップする体制が必要なんだけど、残念ながらそれも今日の霞ヶ関ルールではムリだ。
でも、これを打ち破るのは市民住民の力だ。かれらが自ら動こうとするとき、それが閣議決定であるが故に、霞ヶ関ルールを現場から壊していくだけの可能性を残したんだと思うな。ぼくはいずれ大規模な埋立に関しては住民の賛否を問うような制度が地方から生まれると思うよ。
さ、ぼちぼち今回は終りにしようか。いま選挙戦真っ只中だねえ。でも、争点に環境問題がならないってのは哀しいねえ。
Aさんあーあ、早くワタシにも選挙権が欲しいわ。
H教授まったくキミって奴、いや失礼、キミって娘は年齢詐称の常習犯だな。
あ、そうそう。最後になっちゃったけど、12月13日に鹿児島でボクの講演会を、財団法人 環境情報普及センターの主催でやることになった。
Aさんへえ、ワタシが出なくていいんですか?
H教授(財)環境情報普及センターのなかでもいろいろ議論があったらしいけど、キミは人前に出さないほうがいいだろうということになった。読者を幻滅させたくないという親心なんだろうなあ。
Aさんキー!
注釈
- 【1】首都圏のディーゼル規制
- 神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都の条例により、平成15年10月1日から、1都3県の全域(東京都の島部は除く)において、ディーゼル車の排出ガス規制が実施されている。
対象車両は、軽油を燃料とするトラック、バス、及びこれらをベースに改造した特種用途自動車のうち、初度登録から7年を超えたもの。基準に適合しない車両は、粒子状物質減少装置の装着等が求められる。また、違反車両に対しては、最大50万円の罰金が課せられることとなる。
各都県では、条例に基づいて路上検査等を実施してきたが、10月末の集計結果によると、取り締まり台数計7,139台のうち未対策の違反車両は227台(約3.2%)だったと発表された。
その後、東京都では11月4日に、対策の指導に従わずに走行を続けていた業者に対して、運行禁止命令を出している。対策を取れば命令は解除されるが、未対策のまま再び都内を走行すると業者名公表や罰金もありうるとしている。
一方、環境省では2010年度までにディーゼル車の新たな排ガス規制を導入し、大気汚染の原因となるNOx、PMの排出を、現行規制から最大9割減を目指すとしている。
なお、ディーゼル車の排出ガスは、自動車起源のNOxの約7割とPMのほとんどを占めるとされている。 - 八都県市あおぞらネットワーク
- 東京都 ディーゼル車規制総合情報サイト
- 東京都の大気汚染地図情報
- 国の対応:環境省環境監理局「自動車関係」
- 【2】都市のNOx(ノックス)問題
- 燃焼過程において発生する窒素酸化物をNOx(ノックス)と呼ぶ。呼吸器障害や光化学スモッグの原因となるため、削減・改善が求められている。
発生起源により、燃焼用空気の中に含まれている窒素と酸素とが高温状態において反応し、NOとなることで生成するNOxを「サーマルNOx」、一方、石炭・石油などの燃料中に含まれる窒素化合物の一部が燃焼中に酸化されてNOとなることで生成するNOxを「フューエルNOx」と区別することもある。
窒素含有量の低い燃料を使用すること、燃焼域における酸素濃度を低下させることによってフューエルNOxは削減されてきたが、サーマルNOxは燃焼温度が高く、燃焼域での酸素濃度が高いほど、さらに高温域での燃焼ガスの滞留時間が長いほど生成量は多くなることから、自動車排ガス中などからの発生は改善が困難となっている。
都内排出量約6万7,600トン(1995)のうち、自動車排ガスからのNOxが約7割、さらにそのうちの約7割を、走行量では2割に過ぎないディーゼル車からの排出ガスが占めるとの試算されている。 - 環境省環境監理局「自動車関係」
- 【3】SPM(浮遊粒子状物質)
- 大気中に浮遊している粒子状物質で、代表的な「大気汚染物質」のひとつ。
環境基本法に基づいて定められる環境基準については、粒径10μm以下のものと定義している。発生源は工場のばい煙、自動車排出ガスなどの人の活動に伴うもののほか、自然界由来(火山、森林火災など)のものがある。また、粒子として排出される一次粒子とガス状物質が大気中で粒子化する二次生成粒子がある。
粒径により、呼吸器系の各部位へ沈着し人の健康に影響を及ぼす。年平均100mg/m3になると呼吸器への影響、全死亡率の上昇などがみられることなどが知られている。このためSPMの環境基準は、1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下、1時間値が0.20mg/m3以下、と定められている。
汚染状況について、年平均値は近年ほぼ横ばいからゆるやかな減少傾向が見られる。平成13年度の環境基準達成率は『一般環境大気測定局』で66.6%、『自動車排出ガス測定局』で47.3%である。 - 環境省 環境基準>大気汚染に係る環境基準
- 【4】PM2.5
- 直径が2.5μm以下の超微粒子。大気汚染の原因物質とされている浮遊粒子状物質よりもはるかに小さい粒子で、ディーゼル車が出すディーゼル性排気微粒子など、化学物質が主な成分と見られている。PM2.5はぜんそくや気管支炎を引き起こす。それは大きな粒子より小さな粒子の方が気管を通過しやすく、肺胞など気道より奥に付着するため、人体への影響が大きいと考えられている。
- 【5】環境基準
- 環境基本法第16条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標。人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。政府は公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより環境基準の確保に務めなければならないとされている。大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音について定められている。また、これら基準は、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならないと規定されている。 現在、大気汚染、水質汚濁、地下水の水質汚濁、土壌汚染、各種騒音、およびダイオキシン類による汚染のそれぞれに係る環境基準が設定されている。
- 環境省ホームページより
- 【6】(自動車)グリーン税制
- 燃費効率がよく、排出ガス中のNOx(窒素酸化物)やPM(粒子状物質)などの有害物質を低減した自動車の自動車税や自動車所得税を軽減するための制度。2001年度より2年間の特例措置として導入され、2003年度には排ガス中の有害物質を75%減らす車に限って1年間の延長をしている。
減税分は、性能の劣る13年以上経ったガソリン車、11年以上のディーゼル車の自動車税を重くすることでまかなうこととしている。
国土交通省のまとめでは、新車登録の3台中2台が低公害車となるなど、急速な普及をみせており、10年間で1,000万台との目標を5年前倒しで達成できる見込みとしている。 - 国土交通省「自動車税制のグリーン化」(平成15年9月22日)
- 低公害車ガイドブック
- 【7】 VOC(揮発性有機化合物)
- 常温・常圧で揮発する有機化合物をVOC(Volatile Organic Compounds)と呼ぶ。
VOCは、油脂成分の溶解能や難分解性、不燃性などの特性により、洗浄剤や、塗料・接着剤の溶剤など多くの用途で広く普及してきた。主な用途は、IC基盤や電子部品の洗浄、金属部品の前処理洗浄、ドライクリーニングなど。
一方、吸引によって頭痛やめまいの原因になるほか、中核神経や肝臓・腎臓機能障害、発ガン性を示すことが報告されるなど問題化してきている。近年住宅の室内空気汚染の原因としても注目される。
具体的な物質には、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ジクロロメタン、四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼンなどがある。
環境省では、SPMとオキシダントの生成にVOCが関与していること、また国内の排出量約185万トンは諸外国と比べて単位面積当りの排出量が多く、濃度も高いこと等から、特に固定発生源からのVOCの排出抑制に関する検討会を設置して、法制化に乗り出している。 - 環境省報道発表「揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会の開催について」(平成15年9月18日)
- 環境省 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会
- 【8】非メタン炭化水素(NMHC)
- メタン以外の炭化水素(脂肪族飽和炭化水素、不飽和炭化水素、芳香族炭化水素)の総称。NMHCと記すこともある。
メタンは光化学的に活性が低いため、光化学オキシダント対策で大気汚染を論じる場合にこのような指標が使用される。NMHCは、自動車に対して規制が実施されているほか、塗装、印刷工場などの発生源についても排出抑制の指導が実施されている。 - 環境省環境管理局「非メタン炭化水素濃度の推移」(平成13年度の大気汚染状況より)
- 【9】光化学スモッグと光化学オキシダント
- 工場、自動車などから排出される窒素酸化物や炭化水素が一定レベル以上の汚染の下で紫外線による光化学反応で生じた光化学オキシダントや視程の低下を招く粒子状物質(エアロゾル)を生成する現象、あるいはこれらの物質からできたスモッグ状態のことをいう。 光化学オキシダントとは、工場や自動車排出ガスに含まれている窒素酸化物や炭化水素が、一定レベル以上の汚染の下で紫外線による光化学反応を繰り返すことによって生じる酸化性物質(オゾン、パーオキシアセチルナイトレート、ヒドロキシペルオキシドなど)の総称。 光化学オキシダントの高濃度発生は気温や風速、日射量などの気象条件の影響を受け、夏期の風の弱い日差しの強い日に発生しやすい。オキシダントと同義で使われることがある。粘膜を刺激する性質を持ち、植物を枯らすなどの被害を及ぼす。光化学オキシダントの高濃度汚染が起こるような状態のことを光化学スモッグとよぶ。 1950年ごろに米国・ロサンゼルスで、粘膜の刺激を訴える人が増え、また植物被害が生じる原因不明の大気汚染現象について研究解明が行われ、光化学反応によることが判明した。また、日本では1970年7月18日、東京都の高校生がグランドで運動中に胸が苦しいなどの症状を訴え、約40名の生徒が病院に運ばれ、同日に東京都などで数万人が目の刺激などを訴えたが、これは光化学オキシダント被害であったと考えられている。この頃から日本でも汚染や健康影響が発生するようになった。 環境基準は1時間値0.06ppm以下(窒素酸化物の影響を除いたもの)、注意報基準は 0.12ppmで、警報基準は0.4ppm。
- 環境省環境管理局「光化学オキシダント(Ox)」の測定状況(平成13年度の大気汚染状況 より)(PDFファイル)
- 環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」
- 【10】世界自然遺産
- 人類にとって普遍的な価値を有する世界の文化遺産、自然遺産を、特定の国や民族のものとしてだけでなく、人類のかけがえのない財産として、各国が協力して守っていくことを目的に、第17回ユネスコ総会で1972年に採択された「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」(発効は1975)では、「自然遺産」、「文化遺産」、「複合遺産」を登録して保全を図っている。 締約国は、登録候補地を「世界遺産委員会」に申請し、世界遺産として相応しいと認定されると「世界遺産リスト」に登録される。2002年現在、締約国数は125カ国、登録件数730(自然遺産144、文化遺産563、複合遺産23)。日本は、1992年に締約国になり、11(自然遺産2、文化遺産9)箇所を登録している。 日本の世界自然遺産は、平成5年に登録された白神山地と屋久島の2箇所しかなく、新規登録を目指して平成15年に世界自然遺産候補地検討会を環境省・林野庁が合同で設置、同年5月に3箇所の候補地を選定し、10月に知床を推薦することが発表されている。
- 日本ユネスコ協会連盟「世界遺産最新情報」
- 知床の世界自然遺産推薦に関する小池環境相のコトバ(環境省HP「大臣談話等」より)
- 環境省報道発表「世界遺産条約に基づく世界遺産一覧表への記載に係る今年度推薦作業方針について」
- 【11】赤土流出
- 沖縄や奄美諸島、小笠原等のサンゴ礁域で、降雨により土壌が浸食されて海域に流出すること。 これらのサンゴ礁域の土壌は赤色や暗赤色の成分が多いため、赤土と呼ばれる。裸地状態になった開発工事現場や農用地が主な流出源。 サンゴ礁域に流入する赤土は海水中の懸濁粒子となり、サンゴの体組織に摩擦による損傷を与えたり、光の透過を妨げてサンゴと共生している藻類の光合成を妨げて、サンゴの生育に影響を与える。 また、サンゴは体表に堆積した堆積粒子を除去するために粘液を分泌することによっても多くのエネルギーを消費する。堆積の程度によっては代謝が阻害されて死亡することもある。
- 赤土流出がおきるしくみ(沖縄県衛生環境研究所)
- 【12】国立公園とレンジャー
- 亜鉛の環境基準をめぐって(付:レンジャー今昔物語)
- 【13】総量規制
- 総量規制
- 【14】瀬戸内海環境保全特別措置法と埋立の基本方針
- 瀬戸内海環境保全特別措置法は、1973(昭和48)年に制定された「瀬戸内海環境保全臨時措置法」(議員立法)が、1978(昭和53)年に恒久法化されたもの。
瀬戸内海の環境保全上有効な施策を推進するために、国による瀬戸内海環境保全基本計画とそれに基づく関係府県による府県保全計画の策定、特定施設の設置及び変更にかかわる規制、水質汚濁防止法に基づく総量削減基本方針の策定による汚濁負荷量の総量の削減、関係府県のよる自然海浜保全地区の指定による対策の促進、また埋立てについての特別の配慮 などを定めている。
関係府県は、瀬戸内海沿岸の京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県(2府11県)。
埋立てについての特別の配慮事項として、府県知事は公有水面埋立免許に当たり、「埋立ての基本方針」(昭和49年5月瀬戸内海環境保全審議会答申)に照らし、環境保全上から特別の配慮をしなければならないとされている。 - 「埋立の基本方針」の概要(財団法人国際エメックスセンターHPより)
- せとうちねっと 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対策
- 旧運輸省審議会「港湾審議会」
- 【15】「ミティゲーション」(環境影響緩和措置)
- 人間の活動によって発生する環境への影響を緩和、または補償する行為をミティゲーションと呼ぶ。急激な湿地帯の減少に対処するため、1970年頃に米国で生まれた。ミティゲーションの対象は、現在でも湿地が主流となっているが、必ずしも湿地に限るわけではない。米国の大統領府直属の環境諮問委員会(CEQ)による整理では以下の5段階をあげている。
1) 回避(Avoidance):ある行為をしないことで影響を避ける。
2) 最小化(Minimization):ある行為とその実施に当たって規模や程度を制限することによって環境に与える影響を最小化する。
3) 修正・修復(Rectifying):影響を受ける環境を修復、回復、復元することによって、環境に与える影響を矯正する。
4) 軽減(Reduction/Elimination):ある行為の実施期間中、繰り返しの保護やメンテナンスを行うことで環境に与える影響を軽減もしくは除去する。
5) 代償(Compensation):代替資源や環境を置き換えて提供することで、環境へ与える影響の代償措置を行う。
より簡易に、「回避」、「低減」、「代償」の3段階に分類することも多い。
これらの5ないし3段階はその順に検討することとされるとともに、米国では、ミテイゲーションの結果、環境影響をトータルでゼロにするノーネットロス原則が前提となっている。日本ではアセス法アセスの評価においてミティゲーションの考え方が採り入れられたと言われているもののノーネットロス原則は前提とされていない。
本来的意味合いから離れ、代償ミティゲーションのみをミティゲーションとみる矮小化されることも多い。 - 【16】リゾート法
- 総合保養基地整備法の略称。リゾート産業の振興と国民経済の均衡的発展を促進するため、多様な余暇活動が楽しめる場を、民間事業者の能力の活用に重点をおいて総合的に整備することを目指し制定された法律(1987)。所管は総務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省。都道府県が策定し国の承認を受けた計画に基づき整備されるリゾート施設については、国及び地方公共団体が税制上の支援を行う等の優遇措置が執られる。 41道府県の42地域が国の承認を受けリゾート開発に取り組んでいるが、地域振興策として期待される一方、計画の頓挫や環境保全上の問題を引き起こすなど批判も多い。
- 総務省 法令データ提供システム「総合保養地域整備法(昭和六十二年六月九日法律第七十一号)」
- 国土交通省「総合保養地域整備法の概要」
- 総合保養地域整備法(リゾート法)のあらまし
- ※ 埋立認可は旧運輸省や建設省の権限であったが、認可にあたっては環境庁の意見を聞くことになっており、事業者が県の場合は、計画の時点で県の環境部局との調整を終え、環境庁とも事前調整を行うのが通常のルール。環境庁の窓口はアセス担当課だったが、瀬戸内海での埋立案件は実質的には瀬戸内海環境保全室が調整を行った。
- 【17】燐(リン)
- 総リンはリン化合物全体のことで、無機態リンと有機態リンに分けられる。無機態リンはオルトリン酸態リンと重合リン酸に分けられ、有機態リンは粒子性有機態リンと溶解性有機態リンに分けられる。重合リン酸はリン酸が多数重合した形態でメタリン酸、ピロリン酸等で、人為的影響が強く、分解され最終的にはオルトリン酸態リン(PO4-P、正リン酸又は単にリン酸)になる。粒子性有機態リンは藻類などの体内に取込まれた状態で粒子として存在し、溶解性有機態リンは水に溶解している状態で存在する。リン化合物も窒素化合物と同様に、動植物の成長に欠かせない元素だが、富栄養化になりプランクトンの異常増殖の要因となり赤潮等が発生する。総リンは河川には環境基準値がなく、湖沼・海域に定められている。富栄養化の目安としては、0.02mg/L程度とされている。
この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。
なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
参考: 『H教授のエコ講座 瀬戸内法30年』(「瀬戸内海」第33号/平成15年3月・瀬戸内海環境保全協会
(平成15年10月19日執筆・文:久野武、10月末日編集完了)
※掲載記事の内容や意見等はすべて執筆者個人に属し、EICネットまたは一般財団法人環境イノベーション情報機構の公式見解を示すものではありません。
