No.058
Issued: 2004.07.15
ドイツの森林・野生動物の管理事情混迷を深める「狩猟─林業─自然保護」の三角関係

シュルヒゼー森林所長・ゲレッケ氏
ドイツでの狩猟は、特権階級の独占的なスポーツとされてきました。森でドーベルマンなどの猟犬を連れ、黒光する優雅な革製品の猟銃装備や出で立ちに、帽子と口ヒゲという姿が長らく、そのシンボルでした。ところが、最近では担い手の高齢化と後継者不足、趣味人口全体の減少など、狩猟を取り巻く環境は厳しくなってきています。
趣味人口の減少の背景には、レクリエーション活動の多様化や、ライフスタイルの変化に伴って長時間を要する狩猟が他の趣味と競合しづらくなっている状況があると指摘されます。さらに、猟区の使用権価格の高騰、猟や毛皮製品に反対する動物福祉運動の高揚、以前は決して悪くなかった森林所有者や森林行政などとの関係悪化などが追い討ちをかけています。
今回は、一時は貴族のスポーツとして隆盛を誇りながら、現在では厳しい局面に立たされるドイツの狩猟について、林業、狩猟、自然保護という三者の視点から、ドイツの歴史的な自然価値観、森林政策の変遷の一端を垣間見ていきます。もっと大きなテーマでは「人間─自然」の関係の歴史といってもいいかもしれません。日本でもペットブームとして小動物がもてはやされていますが、今回の話を機会に、人と動物の関係について一緒に考えていきましょう。
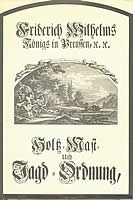
1720年に出版された狩猟規則本の復刻版表紙:貴族的な雰囲気が漂う
【歴史ノート】
ここでは、シカやイノシシなどの大動物を対象とする狩猟(Hochjagd)を示しています。かつてドイツでは、王様はシカ、貴族はノロジカ、庶民はウサギなど身分によって狩猟ができる動物種が決まっていました。中世以降のドイツでは、狩猟は社会の秩序を反映する鏡としての活動だったわけです。ドイツの狩猟は、欧州のなかでも貴族に独占されてきた色彩が濃く、現在でも、狩猟の際の歌、服装、作法に関する本があるほど慣習・マナーも多いことが特色です。
一方「森林官」は、かつては貴族的な職業でした。木材生産の計画と経営と、森林内での違法な行為の取り締まりという、警察官と類似した役割の大きく2つの機能を担ってきました。狩猟の際の規則の遵守を徹底させるのに加え、林業への影響などを考慮する必要から、狩猟者と森林官の関係は密接です。最近では、自然保護やレクリエーションへの対応なども同時に求められています。
頻出する野生動物による林業・農業被害や交通事故

シカなどによる食害を防止するための若木のための柵
野生動物によって農林業が受ける被害には、さまざまな種類があります。まず、筆頭に挙げられるのが、若葉、新しい芽、農作物などが食べられてしまう「食害」です。また、角などを樹幹に擦りつけられることで起きる皮剥ぎの被害、また地盤が緩い個所を大量のカモシカが移動することによって、土砂崩れを引き起こし通行に支障の出る林道もあります。さらに、野生動物が高速道路で轢かれる交通事故が多発しています。ドイツ全土では年間20万件の野生動物に関わる交通事故が発生しており、被害額は5億ユーロ(約75億円)にも及んでいる。昨年2002度のバーデン・ビュルテンベルク州だけでも年間約24,000件弱の事故が発生しています【1】。

交通事故死した野生生物(参考文献より)
このような被害状況を受け、解決策としてさまざまな意見が提案されています。まずは、都市住民の価値観と、農山村における価値観の違いに目を向けてみましょう。
都市住民と農山村の価値観の食い違い: 餌付けはかえって野生動物を危険にさらす!
都市住民のなかには、交通事故で動物が轢かれて可哀想、餌がなくて悲惨と思われる方もいるかもしれません。交通事故で怪我をした野生動物を、森林官がその場で撃ち殺すことに抵抗を感じるケースも多いでしょう。またハイキングなどの途中で餌付けをする観光客も少なくありません。
善意から生じる思いや行動ですが、ペットと違って野生動物は怪我などによって生き延びる力を失った時点が死を意味します。餌付けされた野生動物が人里に戻ってきて、撃たれることもあります。また「州有林や公有林などの森の中と違って、人里近くでは撃たれない」などと、人の出入りの状況や森林の所有形態によって撃たれやすい場所と撃たれにくい場所を学習し、被害が集中することにもつながります。
都市部では、当たり前に見える行為も、実際には野生動物に害を及ぼす要因になることもあるわけです。
林業─狩猟─自然保護の微妙な三角関係
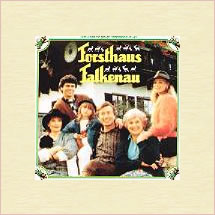
「ファルケンナウの森小屋」
ドイツには「ファルケンナウの森小屋(Forsthaus Falkenau)」という、森林官とその一家を中心としたテレビ番組のホームドラマがあります。20年以上続く定番シリーズで、「大草原の小さな家」のドイツ版というようなものです。番組中の過去10年の変化として、主人公の森林官が猟銃を担いでいるのに使わなくなったことが指摘されます。林業(森林官)と自然保護に対するイメージが変わり、狩猟行為が悪くみられるようになったのです。現在、林業と狩猟と自然保護はさまざまな局面で対立したり、お互いに協力したりして、入り乱れた関係にあります。中心的な論点は、野生動物の生息数をめぐる引っ張り合いです。三者の主張をそれぞれ順番にみてみましょう。
林業サイドの言い分を要約します。野生動物の生息数が多すぎると、新しい芽が食べられたり、樹皮が剥がれたりと被害が大きくなり、木材価格の下落など経済的に厳しい今の状況では生息数を減らしてもらうのが一番【2】。特にドイツの森林政策は、いっさい植林を行わず、さまざまな樹種の芽が自然に出てくる「天然更新」を促進するように移行していることもあって、ある種の樹種だけが野生動物に好まれて食べられた結果、予定していた森林の樹種構成がおかしくなってしまうという事態も生じてしまいます。

歯形がくっきりと残る樹幹:このような傷跡が付くと材木の価値はなくなってしまう
一方で、ハンターにとっては、短い時間でなるべく多くの獲物にありつくチャンスが望まれます。狩猟区画の使用権、狩猟権の価格が高騰し、より多くの獲物が撃てる区画に人気が集中しています。それを受けて冬の間に(抗生物質を混ぜた)餌付けをしてまで野生動物の数を増やそうとする不正な動きもあります。
自然保護団体の立場からは、ことはそう単純ではありません。冬期の餌付けに反対して個体数を制限し、天然更新を促進するという大筋では、林業サイドと路線が一致しています【3】。しかし、希少植物などの特定のテーマや森林管理・野生動物の管理については、林業サイドと距離があるのも事実です。
また、オオカミなど大型肉食獣を導入して、草食動物の数を抑制するという案も自然保護推進派から出ています。実際の個体数減少への効果については、森林管理局の科学者でワイルドライフ・マネジメント専門家のズーハント博士などが疑問を投げかけている一方で、家畜等への被害などを危ぶむ声もあがっており、かつて生息していたオオカミ、ヤマネコ、ハイイログマなどの再導入には至っていません。ズーハント博士は、自然のバランスを取り戻すという考え方自体が人間の発想であり、植生を食い荒らして野生動物の個体数が激減するのも自然のバランスだし、野生動物の個体数が大きく変動することも自然なのだと戒めています。
まとめ
このように野生動物の生息数の議論には、冬期の餌付け、野生動物が新梢を食べてしまうことによる林業への食害や、野生動物による樹皮剥ぎ、林業の方向転換など、さまざまな問題や政策が絡み合っています。林業・狩猟・自然保護の3者の立場から、状況と今後の方向性、提言や政策について、表にまとめてみました。
| 状況と方向性 | 提言・政策 | |
|---|---|---|
| 林業 | 林業経営は、経済的に厳しい状況にある 天然更新で多様な樹種からなる森を! |
柵・薬の投入 動物の計画的捕獲 |
| 狩猟 | 趣味人口の減少とコスト高 短い時間で安く楽しめる猟を! |
若い世代の勧誘・育成 イメージの復権 |
| 自然保護 | 発言権の増大 林産物の生産の場としての森林から、 生態系のための環境を! |
「自然」な土地の確保 肉食獣の再導入の検討 |
野生動物が増えたり、減ったりすること、その個体数の増減だけで善悪は判断できません。より広範囲な視点から野生動物を管理しようとの考え方として、ワイルドライフマネジメントという概念が提唱されてきています。野生動物は、その絶対的な数よりも、人の生活への影響度合いなどによって状況を判断すべきであるとの立場に立ったものです。野生動物の個体数は、異なる立場の人間集団による調整の上に成立しているのです。
利害関係の異なる集団が合意形成を図るするのはたやすいことではありません。合意形成の取り方についても、さまざまな手法や方法が議論されています。
【兵庫県立 人と自然の博物館 坂田宏志主任研究員からのメッセージ】
人と自然の関係の中で、狩猟というのは重要な営みです。日本でも、5,000年以上もの長い間、シカやイノシシなどの野生動物を食料や生活必需品の材料として利用してきました。だからこそ保全の努力も続けてきたのです。
第2次世界大戦争前後には、外貨獲得や軍事上の需要のために乱獲され、全体的に日本の野生動物の数は減っていたため、その保護が重要な課題でした。必要なことは適切な狩猟の管理や生息地の保全なのですが、自然保護の流れは、狩猟の軽視や衰退にもつながったといえます。今、狩猟者の数は、最盛期の3分の1にまで減っています。
しかし、牛や豚などの家畜の利用で、シカやイノシシは獲られなくなり、その数が増えてきました。今日、野生動物による農林業被害や自然植生の衰退が深刻になり、被害防除や個体数の調整のために、たくさんの動物が捕獲されています。かつて、シカやイノシシは捨てるところなく活用されてきましたが、いろいろな事情で、駆除された動物が有効に利用されず、廃棄される場合もあります。狩猟という行為は、感謝とともに自然の恵みを享受し、その恵みの持続的な保全を図る、人間に必要不可欠な行為といえますが、社会的な状況次第で、害獣駆除だけが目的の捕殺になってしまうのです。
今まで続いてきた地域生態系の中の、食うものと食われるものの関係を、一方的に断ち切るわけにはいきません。また、増えて困った動物の処理を、一部の狩猟者に押しつけ、野生動物を殺さなくては生きていけない現実から目をそらすべきでもありません。
鳥獣保護法の改正に基づき、都道府県では、課題のある動物に対しては科学的な計画に基づいて保護と管理を進めていくことになりました。そのためには、適切な狩猟や狩猟資源の有効活用も大切なポイントです。これまでの伝統的な狩猟や資源保全の知恵、獲物の活用方法などを見直すことも必要です。
現在の人と野生動物の共存のためには、地域の生態系の産物を、バランスを取りながら活用するという視点が必要だと思います。そのような認識に立って人と自然の博物館では、野生動物の保護管理に関するセミナーや、被害現場などの実情を知るためのセミナー、シカ肉の有効利用のための料理教室などを開催しています。被害現場での見聞や、捕獲された動物の姿、狩猟者や被害者、保護論者との直接的な議論などは、参加者なりに野生動物とのつきあい方を見直す機会になっていると思います。また、自然の恵みのおいしさも好評です。
直接狩猟をしない人も、狩猟という営みを、生態系のバランスや社会的課題との関係も含めて、さらには捕獲するところから食べるところまで考えて、そのあり方を考え直すべき時期にきているのだと思います。坂田宏志(兵庫県立人と自然の博物館)
- 【1】野生動物の交通事故
- 動物種別には、ノロジカの2万件とイノシシの2,300件が大部分を占め、この他にもアカシカ、ダマジカ、カモシカなどが続きます。
- 【2】野生動物による林業被害について
- 実際にも若葉や新芽などへの食害状況を3年おきに森林官が評価して、猟区内で撃つ適正な個体数が算出されています。
- 【3】自然保護─林業の関係について
- もちろん、動物愛護の視点から、狩猟自体に反対する団体も数多く存在しますが、連邦政府の狩猟法の改正の際などには、大手の自然保護団体と林業が連立して、狩猟サイドと議論したことなどもありました。
関連情報
- 兵庫県立 人と自然の博物館
- イギリス政府 スポーツ狩猟 非合法化への動き(関連プレスリリース)
- フランス 狩猟期間の協議 狩猟協会vs自然保護協会(関連プレスリリース)
参考図書

キャプション
- Link, Fritz-Gerhard編集 2001 Ein Brückenschlag für Wildtiere.
Stuttgart市 Akademie für Natur- und Umweltschutz (Umweltschutzakademie) beim Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg
この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。
なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
本稿の内容は、兵庫県農林水産部農林水産部森林動物共生室の取材調査に同行した体験をもとに、同県担当者の許可を得て独自の記事として作成したものです。執筆に当たり、フライブルク大学 環境・森林学部のゲラルド・オステン教授とウルリッヒ・シュラメル博士に助言をもらいました。
(記事:香坂玲、坂田宏志)
※掲載記事の内容や意見等はすべて執筆者個人に属し、EICネットまたは一般財団法人環境イノベーション情報機構の公式見解を示すものではありません。
