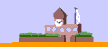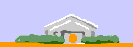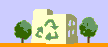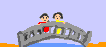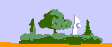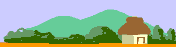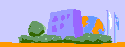いろいろなどんぐり
目的
- 気づき:身の回りにある自然に気づく
- 知識:どんぐりの種類と、どんぐりを実らせる樹種について知る
- 行動:どんぐりと動物の関係など、生物同士の共生に学び、自然と共生できる生活を送れる
背景
タネと実
植物の種子(タネ)は、顕花植物(裸子植物と被子植物)が受精によって形成する繁殖体で、種の保存という大役を担っています。種子から発芽した植物は、根がある程度生長して、独立的に栄養吸収できるようになるまでは、種子の内部に持っている親植物から授かった栄養分に依存して生育します。
一方、木の実は、植物学的には木本植物〔木〕の(被子植物の)子房が発達した組織〔実〕といえますが、一般には文字通り「木になる実」を指し、ギンナンやマツの実などの裸子植物の種子も含んで解釈されることが多いようです。また、ウメやモモなどの「タネ」(芯)は、果実の内果皮が硬化した核と呼ばれる器官で、種子はその内部にあります。
タネの戦略
植物は自分自身で移動ができないため、分布を広げるための戦略は主に種子を拡散することによって行います。どんぐりなどの木の実は雌しべの子房が肥大化したもので、中に種子が守られています。リンゴやナシなどのように、花を支える花床もいっしょにふくらんだものや、松ぼっくりのように種子を松かさに挟んで守るものもあります。枝から落ちて転がって分布を広げたり、風によって種子を拡散するもの、動物に果肉を食べさせ、中の種は固い殻に保護して糞といっしょに排出されることで種子の拡散をねらうものなどもあります。
どんぐりの種類と形
どんぐりとは、本来クヌギの実を指していう言葉ですが、通常カシ、シイ、コナラ、カシワなどブナ科の木の実を総称して「どんぐり」と呼ぶことが多くなってます。したがって、大きさや形も樹種によって異なります。コナラやマテバシイのように細長いどんぐりや、クヌギ、カシワなどの丸い実などがあります。また、どんぐりには「殻斗(カクト)」と呼ばれる小さなお椀状の帽子がついています。これも木の種類によって形や大きさが異なります。常緑樹のどんぐりは殻斗に模様がついており、落葉樹のどんぐりは殻斗が鱗状だったり房のようになっています。
どんぐりと人間の関わり
かつて、日本ではどんぐりやトチの実、クルミなどを集めて食料にしていた時代があったことがわかっています。縄文時代には主要な食料だった他、数十年前までは国内各地の山村で木の実を食品の一部にしていた文化がありました。また、子どもたちがどんぐりを拾っておもちゃとして遊ぶことも文化もありました。
発展
タネの戦略
植物は、種子拡散のためにさまざまな戦略を取っています。どんぐりをつけるカシ類やナラ類は恐竜時代に進化したと考えられています。この時代、どんぐりを食べる動物はいなかったため、後の時代に進化した人間や、リスやネズミなどの小動物がどんぐりを食べることに対しては無防備であると考えられています。しかし、リスやネズミなどの小動物がエサとしてためたものの食べ残しや食べ忘れが芽を出し生長することも多く、これらの小動物によって集められ、貯められることで分布を広げることもあります。
この他、動物のからだにくっついて遠くに運ばれたり、長い年月芽を出すチャンスを待っていたりと、植物は知恵を絞って子孫を残す工夫を凝らしています。さまざまな種類の種子が、それぞれどのような戦略を持ち、それを実現するためにどのような形態へと発達してきたか、また他の生物とどのような関係にあって、生物界の中でどのような役割を果たしているか等について捉えることが重要といえます。
木の実と人間文化
人は、昔から植物をさまざまな形で利用してきました。食べる ・遊ぶ ・役立てるなど、主に種を使った植物の利用方法について調べ、また実際に体験してみる展開も図れます。
アワのたつ実:エゴ、ムクロジ、エンジュ、サイカチなど
食べる:ヤマモモ、クワ、ウメの実など
木の実で染める:ヤシャブシやハンノキの実など
和ロウ:ハゼの実
油:ツバキの実
関連情報
- どんぐりボランティアネットワーク
- 〒〒760-0017 香川県高松市番町4-1-10 香川県林務課内どんぐり銀行事務局
TEL: 0878-31-1111(内2696)
FAX: 0878-61-5302